ニュース その他分野 作成日:2018年12月14日_記事番号:T00080979
みずほ銀行セミナーレポートみずほ銀行主催の「2018年みずほ講演会」が11日に台北市内で開催され、日本人や台湾人ビジネスパーソンなど約250人が参加した。同講演会は年に2回開催しており、今回は今年2回目の開催だ。10日に高雄支店、12日に台中支店と、みずほ3拠点で開催した。
本稿では、講演会の概要を掲載する。
第一部 ~為替市場動向~
みずほ銀行 グローバルマーケッツ業務部 台北資金室長 能勢和宏氏
 みずほ銀行 台北資金室室長 能勢和宏氏
みずほ銀行 台北資金室室長 能勢和宏氏
18年を振り返ると、▽2月に米金利の上昇を受け、世界的株安▽4月に米10年債利回りが3%台へ上昇▽8月にトルコリラ、アルゼンチンペソが急落▽10月に米長期金利の上昇を受け世界的な株安──など、米金利上昇がトリガー(引き金)となり、為替・株式市場が大きく変動した1年だった。
その中、台湾ドルについては、年初来の値幅が5%程度であり、近年最低の値幅を記録すると見込まれる日本円(約9%、10円)と比較しても安定した相場が続いている。さらに、過去10年間さかのぼってみても、20%のレンジ内で動いており、他の通貨と比較しても安定している。台湾の通貨を観察するに当たり、金利・為替に関する要人発言が限られるため、米ドル、日本円、人民元といった他の通貨の動きを見ながら、方向感を把握する他、為替を予想するに当たっては海外動向を注視する必要もある。具体的には外国人投資家による株式売買動向を参考にしながら方向感をつかめる。
19年に関しては台湾ドル経済は減速傾向となると予測する。台湾単体がスローダウンというより、中国を含めたアジア地域全体がスローダウンする見込みだ。
米ドルについては、米長期金利の上昇などを背景にドルインデックスは上昇基調で推移している。その中、金利を操作する米連邦準備制度理事会(FRB)の今後の動きに注目する必要がある。FRBは最大限の雇用と物価水準を課題としている。雇用に関しては現状ではほぼ完全雇用に近い状態で、物価水準も目標値の2%に近い水準に来ている。賃金(平均時給)も10月は前年比+3.1%まで上昇し、物価の上昇基調をサポートしている。
直近のFRBのハト派化で19年の利上げ織り込みが年0.4回程度まで下がってきているが、株価急落からの逃避的な動きとも言えるため、その分は割り引いてみる必要がある。年0回とすると米のリセッション(景気後退局面)があるということに等しいが、みずほ行内ルートでの各国要人の発言からは、多くは19年の米景気スローダウンは可能性としてあるものの、リセッション入りはないとみている。ただし、長短金利差が縮まっていることは事実であり、過去20年でIT(情報技術)バブル崩壊とリーマンショックの際に長短金利差がマイナスになったが、その後リセッション入りしているため、逆イールド(長短金利の逆転)になることを市場が意識し始めている点には注意が必要だ。
ドル円については、実行為替相場からみてドルが割高、円が割安となっており、特に円についてはみずほ銀行ではPPP(購買力平価)のコアレンジを95~105円とみており、19年にはFRBの過剰な引き締めの反動等から過度な円安が修正され、金利・為替が折り返し、19年年末には103円になると予想している。
人民元は1ドル=7人民元の攻防が続き、中国当局としては資本流出を回避するためこのレベルは死守したい。10月以降各種施策を打ち出すと同時に為替介入も行っており、当面は1ドル=7人民元は守られるだろう。
最後に、来年に関しては、3月29日の欧州連合(EU)からのイギリス脱退のタイミングで米中関税引き上げの90日延長の期限を迎えることに加え、グローバルなビッグイベントが3月に集中しているため、相場水準がジャンプすることも想定しないといけないと述べた。
第二部 ~次世代モビリティによる産業・社会の変化~
みずほ銀行 産業調査部次長 蜂谷勝之氏
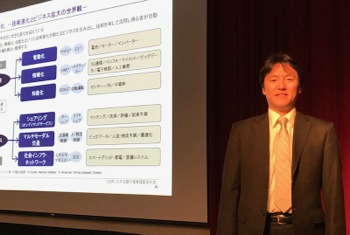 みずほ銀行 産業調査部次長 蜂谷勝之氏
みずほ銀行 産業調査部次長 蜂谷勝之氏
第二部では、自動車の変化が自動車産業および社会にもたらす変化について、解説した。冒頭に「自動車」から「モビリティ」へ、という概念を説明し、今後はプロダクトとしての自動車からサービスとしてのモビリティへ変化する。現在自動車業界にとって、百年に一度と言われている大きな変化を迎えている。技術の変化といえば、具体的には、電動化、知能化、情報化が挙げられる。ビジネスの変化においては、シェアリング(カーシェアリング、ライドシェア)、マルチモーダル交通(交通網が情報によってつながり、制御され、交通の利便性を高めるサービス)、社会インフラ・ネットワーク(分散型エネルギーマネジメント)が挙げられる。上記で述べた技術の進化が新たなビジネスを生み出し、今後は技術を有して活用できる者が自動車ビジネスの市場を創出・獲得する。
続いて、蜂谷次長は電動化、知能化、情報化においてそれぞれの現状と今後の展望について説明した。自動車電動化の進展は
1.脱炭素の流れで、主要国における環境規制の厳格化
2.完成車メーカーによる電動車シフトと新規参入
3.規模拡大によるコストの低下と技術の進化
の三つの理由から、既に不可逆的な流れとなっていると指摘した。また、EV普及に向けて、電池やインフラ面で多くの課題が残されていることも述べた。
知能化、いわば自動運転の部分に関して、6段階に区分される技術レベルで、アウディは既にレベル3自動運転車の商品化を実現した。さらに、ゼネラルモーターズ(GM)は19年に無人タクシーサービスを開始すると発表した。
ドライバーレスカーの実用化は、追加機能が付加されるという点で、自動車部品サプライヤーに機会をもたらす。自動車の基本機能として求められる「走る」「曲がる」「止まる」は自動運転になっても、変わることはないが、人間が担当する「認知」「判断」「制御」は機械が代替する。そのため、認知機能にはセンサー、判断機能にはAI(人工知能)・半導体、制御機能には統合制御ユニットといった部品の需要が増えるだろう。その一方、認知補助として利用されるミラー、操作入力として利用されるペダルや伝動部品のシャフトといった部品は無くなる可能性もある。
最後に、今後の発展について、自動車の電動化、知能化、情報化およびMaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス)の進展はそれぞれが自動車産業に大きな影響を及ぼすが、相互に関連し合い一体化していくことで、30年代半ば以降にモビリティ革命が実現すると考えられる。モビリティ革命は都市・街のあり方、人々の暮らし・ライフスタイルに大きな変化をもたらす。モビリティ事業の成否は、自動運転によるコスト構造の転換、もしくは付帯事業、例えば交通システム協調や決済・金融、またはデータ利活用事業などでの収益化にある。多数のユーザーを獲得し、さまざまな事業者が提供するサービスを載せるプラットフォームを握る者が利益を享受する。誰がその役割を担うか、その鍵はユーザーのデータをいかにして囲い込めるのかにあると述べた。
第三部 ~台湾経済の現状と展望~
みずほ総合研究所 調査本部 アジア調査部 部長 平塚宏和氏
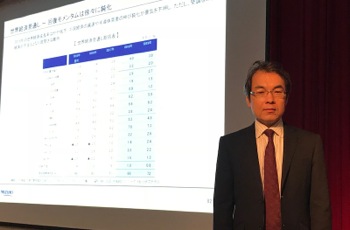 みずほ総合研究所 アジア調査部部長 平塚宏和氏
みずほ総合研究所 アジア調査部部長 平塚宏和氏
本部では、世界経済の現状と展望、台湾経済の現状と展望に分けて解説した。世界経済について、全体的に19年の世界経済成長率は18年の4%から3.8%とやや低下すると予測している。中国経済の減速や半導体需要の伸びの鈍化が景気を下押ししているものの、堅調な米国経済が下支えとなり、底堅さを維持する見通しだ。さらに、GDP(国内総生産)成長率の詳細をみていくと、18年7~9月期の成長率は米国が高水準を維持する一方、ユーロ圏や中国が低下、日本はマイナス成長に転落した。また、製造業の景況感を表す製造業PMI指数(購買担当者景気指数)では、グローバルに年初来鈍化傾向が続いており、新興国は50近辺まで低下してきている。いずれもグローバル景気にピークアウトの兆しが見える。そこで、注目してもらいたいのは、現在の世界経済の状況と15~16年の世界的な景気減速時との共通点だ。16年は中国を中心とした新興国経済の減速が米国、ユーロ圏など先進国経済にも波及している。現状では、中国経済の減速、半導体売上高の伸びが減速基調に転化、原油価格の足元急落など、当時と似た状況が見られ始めている。米中貿易摩擦の激化などで一段と下振れリスクがあるほか、今後は米国経済の変調にも警戒しないといけない。
続いて、台湾経済について、17年半ば以降景気は拡張局面にあるものの、18年7~9月期には減速局面に接近している。また、6カ月先の見通しに関するPMI指数は、製造業・非製造業とも50を下回って低下しており、先行きの景気の減速局面入りがうかがえる。今後の見通しについて、19年の実質GDP成長率は、18年の+2.5%から+2.2%とやや低下する予想だ。
その理由は下記三つ
1.IT需要のピークアウトや中国の成長率低下を背景に輸出は減速
2.個人消費は、米中貿易摩擦をめぐる不透明感や株価の下落などがマインドを下押しするが、良好な雇用・所得環境が一定程度下支えする見込み
3.総資本形成は半導体メーカーの大規模投資後の反動減の一巡、公共投資の拡大、民間建設投資の底打ちといったプラス材料から回復基調を維持する見込み
最後に、平塚部長は11月末に行われた地方選挙の結果が台湾経済に与える影響についても解説した。与党民進党の大敗が20年1月に予定されている総統選の情勢に不透明感を漂わせている。現政権が進めている投資強化政策が進みにくくなる懸念が高まりつつある一方、仮に次期総統選で国民党が勝利した場合、中国との緊張関係が緩和され、対中ビジネス拡大や中国人訪台客の回復を期待する声も高まっている。

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。

ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722